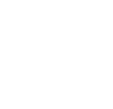鹿児島県立楠隼中高一貫教育校「シリーズ宇宙学」


2025年6月上旬から7月中旬にかけて、鹿児島県立楠隼中高一貫教育校(以下:楠隼高)で「シリーズ宇宙学」の一環として、宇宙産業人材の育成を目指した特別講義・ワークショップが全7回に分けて実施されました。
楠隼高は、様々な分野の第一線で活躍する次世代のリーダーを育成するために、特色あるさまざまな教育活動を展開しています。2015年の創立以来同校で実施されている「シリーズ宇宙学」は、宇宙に関する学びから生徒の探求心を育成するプログラムです。本プログラムにおいて、2023年より特別講義・ワークショップが行われており、QPS研究所とQPS研究所のパートナー企業も一昨年・昨年に続き特別講義を担当してまいりましたので、その模様をご紹介させていただきます。
○特別講義 第2回:6月12日(木)「小型衛星・ものづくりの挑戦 衛星の作り方AtoZ」
2025年度第2回目の特別講義は、昨年度に引き続きQPS-SARの設計・製造に携わる3名がタッグを組み講師を務めました。QPS研究所のパートナー企業からオガワ機工株式会社 副社長 伊藤慎二氏(以下:伊藤氏)と株式会社昭和電気研究所 主幹技師 古賀圭氏(以下:古賀氏)、そしてQPS研究所からは執行役員/開発部長 上津原正彦(以下:上津原)が、各自担当分野について講義を行いました。
9:40、2時限目の授業開始のチャイムと共に特別講義スタートです。この日の講義ではワークショップも実施するため、楠隼高校1年生、計2クラスに10チームの班に分かれてスタンバイいただきました。
まずは当社スタッフより、SAR衛星およびQPS-SARの特徴と本日の講師陣3名をご紹介させていただきました。そして講義開始早々、生徒さんたちに『衛星の作り方』を工程順に並べてもらうワークショップが始まりました。衛星を作るために必要な工程を1〜26までバラバラの順番でお渡しして、それを班で相談して並び替えるのです。各班、相談する生徒さんたちの声で、教室内は徐々に活気を帯びていきます。ひとまず各作業工程を熟考する班、とりあえず目に見える形で並べてみる班、講師陣に質問する班など、班ごとに特色が現れます。

「こっちが先じゃない?」「いやいや、これはココでしょ」とワイワイ賑わうこと15分、あっという間に答え合わせの時間となりました。
各班に模範解答用紙が配られ、上津原から解説を差し上げました。「正解を配りましたが、実はここに書かれている手順だけが正解とは限りません。私たちがこのような流れで衛星を造っている一例であって、皆さんが一生懸命考えられた手順も正解となります」、と衛星開発はミッションとアイデア次第で自由な発想で進めることができる旨をお伝えしました。生徒さんたちは耳慣れない衛星開発用語にも真剣に耳を傾けてくださいました。
続いて、講師は上津原から伊藤氏へバトンタッチし、機械設計・組立において重要なことをお伝えする講義へ移りました。伊藤氏は「トライアル&エラーを何回も繰り返していく」大切さを掲げ、「実際に何が起こっているかを確認し、ブラッシュアップしていく過程がエキサイティングで面白い」、と生徒の皆さんに伝えます。伊藤氏から一つ一つ発せられる重要ワードを熱心に書き留める生徒さんたちの姿が印象的でした。「自分で考えて、正解との違いを見る。自分が思っていたものと違う、それを知ることが大事。その過程でいろんなことが身に付いていくと思います」と、伊藤氏は生徒の皆さまへ期待を込めたエールを送りました。

ここでチャイムが鳴り、特別講義前半は終了し、10分休憩へ入りました。生徒の皆さまは各々トイレ休憩などで教室を退室されるかな、と思っていましたが、わらわらと講師陣のもとに集まってきました。10分という短い時間ながらも3名の講師陣は生徒さんからの質問に対応させていただきました。
10分休憩の後、QPS-SARの電気的部分を担当する古賀氏による講義が始まりました。QPS-SARが稼働するためには多量の電力が必要との説明があり、その電力を得るために必要な電気の仕組みやバッテリーについてもスライドで紹介。さらに、QPS-SARの姿勢制御を行うリアクションホイールの説明には、実際に模型を使って古賀氏と伊藤氏が実演。興味津々に身を乗り出す生徒さんたちに、伊藤氏と古賀氏はゆっくりと各班を回って一人一人に実演くださいました。
古賀氏は、「今回の授業が将来楽しく仕事をするきっかけになれたら嬉しい」、と自身の経験も踏まえ、好きなことが努力の原動力となることを生徒の皆さまに伝えました。
授業終了のチャイム直前まで熱心に質問をいただき、今年度第二回目の特別講義は終了。講義を終えた講師陣も「今年も積極的に参加して考える生徒さんとご一緒できたことが大変嬉しい」と手応えを感じられていました。
〇特別講義 第3回:6月19日(木)「九州発宇宙ビジネスの挑戦」
本年度第三回目となる特別講義の講師を務めたのは、当社 代表取締役社長 CEO 大西俊輔(以下:大西)、ファウンダーで九州大学名誉教授の八坂哲雄(以下:八坂)、そして営業本部 ソリューション事業部長 平田大輔(以下:平田)です。今回の特別講義では「九州発宇宙ビジネスの挑戦」をテーマに、初の試みとなる『宇宙ビジネスコンテスト』を開催いたしました。
まずは生徒の皆さまに向けて、講師3名より自己紹介を兼ねて各々の宇宙ビジネス論並びに人生論のスピーチを行いました。トップバッターは年の功で八坂から。「スピーチのテーマを忘れちゃってね。今日は自分の話をします」、の八坂の開口一番に教室には笑いがこぼれ、空気は一気に和みます。現在83歳の八坂は、これまで多くの人との関わり合いの中で触れた、自分の強み・良いところについて自問自答しました。そして自分の強みは「経験」であると提言した後、その行程は様々な分岐点があり、生徒の皆さまにも分岐点に立った時、後悔しないための選択を大切にしてほしいとお伝えしました。

次に大西のスピーチへと移りました。大西は今現在、宇宙に携わる仕事をしている自身について、小学生時代にブラックホールに興味を持った探求心、さらにペットボトルロケット教室に参加したエピソードをお話ししました。幼少期より「モノづくり」が好きだったこともあり、「宇宙の謎を解く装置を作ることが楽しい」。この「楽しい」が現在の自分に繋がっており、高校一年生の皆さまに向け、今後の進学・進路の参考になれば、と自身の大学や就職の進路選択の過程をお話しいたしました。
講師陣最後のスピーチは平田より、自身がもともと静止衛星のエンジニアから宇宙ビジネスに携わるようになった経緯をお話しました。ビジネスにおける人工衛星、中でもSAR衛星での災害の状況把握、海洋のオイル漏れ検出などの事例を紹介。また、スペースデブリ(宇宙ゴミ)の現状と対策法についてもお伝えしました。そして様々なビジネス経験を踏まえたうえで、「人生で変えられないもの・変えられるもの」について言及し、「自分を変えると未来を変えられる」と生徒の皆さまにメッセージを送りました。
講師陣それぞれ、高校一年の皆さまに今だからこそ伝えたい想いをお届けし、いよいよ『宇宙ビジネスコンテスト』の時間となりました。
『宇宙ビジネスコンテスト』は、事前に生徒の皆さまに「地球の課題を宇宙データで解決する」をテーマに宿題とさせていただいておりました。生徒の皆さまには事前に11チームに分かれて事前準備いただき、コンテスト当日は各チーム5分の持ち時間で発表いただきました。

一分前の雰囲気とは一変し教室内は静寂に包まれ、トップバッターチームのプレゼンテーションが始まりました。各人、同級生のプレゼンテーションに興味津々に耳を傾けます。『交通事故・交通渋滞問題の解決』、『大気汚染問題の予測』『宇宙食を活用し食文化を守る』『農場・牧場地の状況把握』『食糧問題』『災害対策』など、衛星データやAIの活用、宇宙からの視点での課題解決からビジネスにつなげる道筋を全11チームに紹介いただきました。
また、各チームのプレゼンテーション後には、本日の講師陣より講評を述べさせていただきました。三者三様の専門家ならではの視点で、生徒さんが掲げた課題についてのさらなる提案や時に忌憚のない率直なコメントもありましたが、生徒の皆さまは真剣な表情で各講評を受け取ってくださいました。
11チーム全てのプレゼンテーションが終わり、「コンテスト」の名のもと表彰式が行われました。プレゼンテーションが終わりホッとしたのか、教室は少し賑やかになり和やかな雰囲気の中で発表となりました。今回審査員を務めたのは本日の講師3名。最優秀チームにはQPS研究所のオリジナルアイテムが贈呈されました。さらに、特別賞として「八坂賞」「大西賞」「平田賞」として、講師3名それぞれ印象深かったチームを選定し、選定理由の感想を告げると共に自らが感銘を受けた書籍をプレゼントいたしました。

今回の特別講義は、期末試験直前にもかかわらず、楠隼高一年生のみなさまそれぞれ創意工夫を凝らしたプレゼンテーションを披露してくださいました。漠然と「宇宙」というテーマではなく「ビジネス」を絡めた題目は、社会人経験のない生徒さんには想像しにくい部分があったかと思いますが、それぞれの視点で収益化までを見込んだビジネス要素を試行錯誤いただけたことに大変感銘を受けました。
プレゼンテーションの表彰の際に八坂が言った一言、「久しぶりに大変良い時間を過ごさせてもらいました」はまさにその通りで、今回参加させていただいたQPS研究所スタッフ全員の気持ちを代弁する統括となりました。楠隼高からの帰りの道中のフェリーからは、見事な桜島。今年の特別講義も晴れやかな気持ちで講師陣一同は帰路につきました。

この度、QPS研究所とパートナー企業スタッフ一同、2週にわたり講師として伺わせていただき、楠隼高の生徒の皆さまのイキイキと授業に臨む姿に元気をいただきました。今回の特別講義とワークショップが、生徒の皆さまの知識と経験の一部になれれば幸いです。生徒の皆さまのさらなる進歩とご活躍を祈っております。